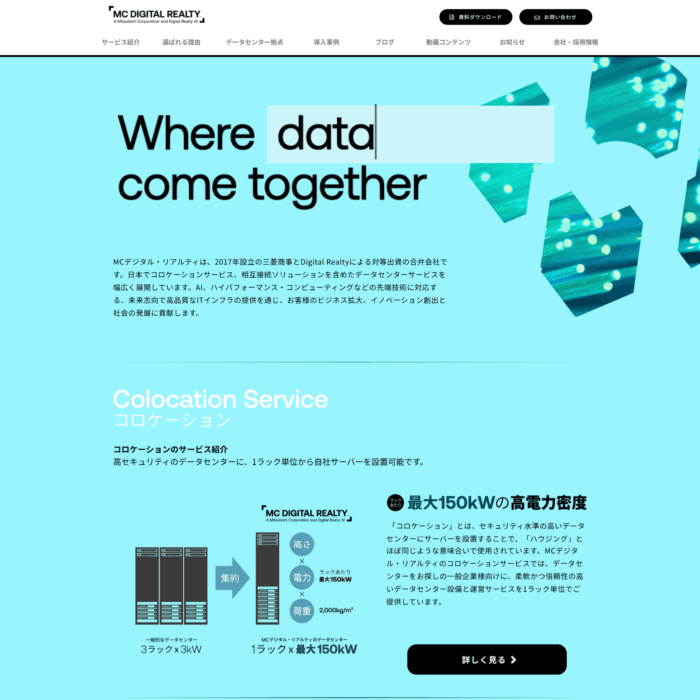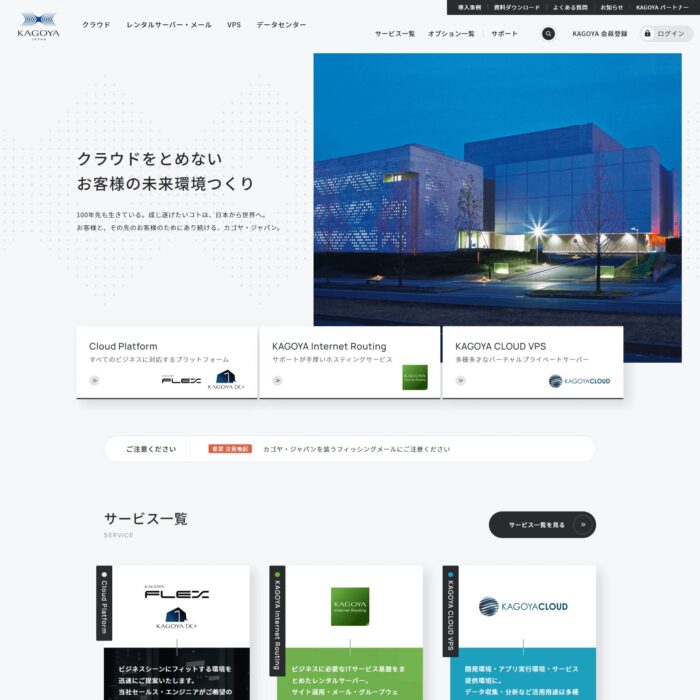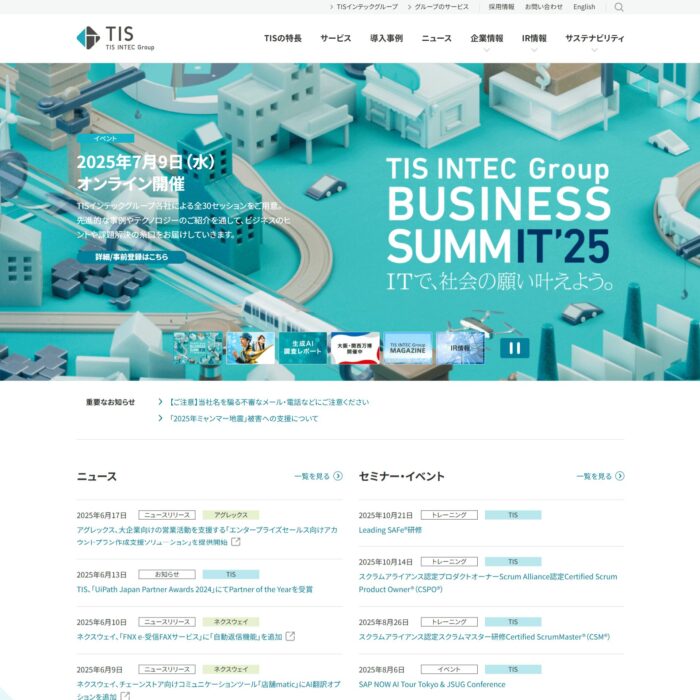サーバーは大きな負荷が生じることもあり、放置しているとさまざまな不具合が発生してしまう可能性があります。そのため、適切なタイミングでリプレースを実施することをおすすめします。この記事ではサーバーリプレースを検討すべきタイミングや判断基準、そしてリプレースの全体的な流れや手順についてくわしく解説します。
目次
サーバーリプレースとは?
サーバーリプレースは稼働中の古くなったサーバーから別の新しいサーバーに取り換えることです。サーバーは企業の情報システムの中核を担う大切な機器です。しかしサーバーもパソコンと同じように消耗品のため、長く使用しているとその性能は低下し、故障のリスクが高くなります。たとえば処理能力が低下して業務効率が悪くなることもあるでしょう。
定期的に行うことで、サーバーの性能を維持して故障リスクを回避できます。
サーバーリプレースをしないと起こるリスク
サーバーリプレースを放置すると、さまざまなリスクが起こる可能性があります。1つ目に「データの消失リスク」です。サーバーは精密機器のため、一定期間を過ぎると劣化が生じます。サーバー内部のハードディスクが摩擦で故障するなど、年数が経過すると劣化は避けられません。
経年劣化したサーバーを無理に使用し続けると、ある日突然故障するため、サーバー内部にあった重要なデータがすべて消失してしまう…というリスクもあります。
2つ目に「セキュリティリスク」です。サーバーリプレースを行わないと、サーバー上で使用しているOSやハードウェアのサポート期間が終了してしまう可能性があります。
OSサポートが終わると、サーバーのセキュリティに脆弱性が生じるため、外部からのサイバー攻撃を受けやすいです。サイバー攻撃を受けると、社外秘データの漏洩、消失、改ざんのリスクも高まるでしょう。
サーバーリプレースをしないと業務効率が低下する恐れあり
サーバーリプレースを行わないでいると、サーバーの処理能力が低下し、業務効率が下がってしまう可能性が高いです。業務効率が下がってしまうと、会社全体の生産性が低下します。自社利益が減ったり、モチベーションが下がったりと会社にとってはよくありません。サーバーリプレースを放置することで企業にとってマイナスでしかないので、必ず早めに対処しましょう。
サーバーリプレースが必要か判断する基準とは?
サーバーリプレースが必要かどうか判断する基準はいくつかあります。1つ目にサーバー導入後5年以上が経過している場合です。サーバーは耐用年数が6年と定められており、導入後5年でリプレースするのが一般的です。メーカーは最低6年間は運用できるように設定していますが、利用頻度や処理量により寿命は異なります。経年劣化が早く進んでいるサーバーについては、5年を待たずにリプレースするべきでしょう。
2つ目にOSやハードウェアのサポートが後1年で終わってしまう場合です。サーバーリプレースはすぐに完了するわけではなく、1年以上かかることも少なくありません。
サポートが切れるとセキュリティリスクが高まってしまうため、OSやハードウェアのサポート年数があと1年を切っている場合には、できるだけ早めに対応しましょう。
3つ目に処理スピードが以前より遅かったり、すぐに故障したりする場合です。明らかに以前よりも処理スピードが遅くなったと感じた場合は、サーバーリプレースのタイミングと言えます。
サーバーリプレースの目的
 サーバーリプレースをするおもな目的は、ハードウェアの老朽化によって発生するトラブルを未然に防ぐことにあります。サーバー内部に搭載されているCPUやメモリ、ハードディスクなどは、長期間の使用によって徐々に劣化していきます。
サーバーリプレースをするおもな目的は、ハードウェアの老朽化によって発生するトラブルを未然に防ぐことにあります。サーバー内部に搭載されているCPUやメモリ、ハードディスクなどは、長期間の使用によって徐々に劣化していきます。これにより、処理速度の低下や予期しないエラー、システムの不具合など、業務に支障をきたす問題が生じる可能性が高まります。とくに業務の中核を担うシステムではこうしたトラブルが業務全体に深刻な影響を与えることもあるため、事前に対策をしておく必要があります。
また、ハードウェアの性能が時代遅れになることで新しいOSやソフトウェアへの対応が困難になり、最新のシステム環境を導入できなくなることもあります。
さらに、古いソフトウェアはサポート終了により更新が止まり、セキュリティの脆弱性を突かれるリスクが高くなります。これらを防ぐには一定の期間ごとにサーバーをリプレースし、常に安定したシステム環境を維持することが重要です。
サーバーリプレースを行うべきタイミング
サーバーのリプレースを行うタイミングとして、一般的に5年がひとつの目安とされています。多くの企業が5年ごとにサーバーを更新している理由は税法上で定められた耐用年数にあります。国税庁の規定ではパソコン以外の電子機器の法定耐用年数は5年とされており、これにもとづいて減価償却も完了するため、更新のタイミングとして適していると考えられています。
サーバー導入から5年が経過している場合は支援会社などに相談したうえでリプレースを検討するとよいでしょう。ただし、5年を過ぎても問題なく稼働しているサーバーもありコスト面や予算の都合でリプレースを先延ばしにするケースもあります。
負荷の少ないシステムや高性能を求めない用途であれば、5年での更新が必ずしも必要とは限りませんが、ソフトウェアのサポートやメーカー保守が終了してしまうと、不具合が起きた際に適切な対応ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
また、24時間稼働が続くシステムや処理速度を重視する業務用サーバーなどは、5年未満でのリプレースが望ましいケースもあります。サーバーの使用状況や役割に応じて、適切なタイミングでの更新を検討しましょう。
サーバーリプレースをしないとリスクはある?

サーバーリプレイスの必要性
サーバーは何十年も使えるものではなく徐々に劣化していくため、不具合が起きてしまう場合もあります。サーバーはとても大切なので、不具合やトラブルを回避するべく交換しておく必要があるでしょう。ここではサーバーリプレイスの必要性について解説します。サーバーの劣化
サーバーを使い続けていると劣化し、昨日は低くなったり動かなくなってしまったりすることがあります。サーバーは365日動いているため、劣化していくスピードがとても早いでしょう。時期を見計らって定期的にサーバーを交換しておかないと、突然動かなくなってしまう事態になりかねません。万が一突然サーバーがストップしてしまった場合、会社のシステムが落ちてしまったり、サービス提供できなかったりする事態に発展してしまいます。
サーバーはいつか必ず壊れてしまうということを前提に、定期的に交換する必要があると心得ておくとよいでしょう。適切な時期にサーバー交換しておけば、安心してサーバーを使い続けられます。
保守が終わる
サーバーやハードウェアには保守がついているのですが、その保守期間が終わってしまうのは大きなリスクです。保守期間が終わってしまうと万が一の際のトラブルや故障などに対応してもらえないでしょう。サーバーやハードウェアを提供している会社が保守期間を定めているため、保守期間がどのくらいなのかというのも意識しておく必要があります。保守期間が終わってしまう前にサーバーを交換しておかないと、対処できない事態に陥ってしまうでしょう。
また、保守期間が切れてしまうとセキュリティーにも影響します。保守期間が終わってしまうとセキュリティーが弱くなってしまうため、ハッキングのリスクやデータが盗まれてしまうリスクが高まります。
サーバーは物理的に劣化してますが、OSやハードウェアの保守期間も考慮してサーバーリプレイスすると安心です。最悪の事態を避けるためにも定期的にサーバーリプレイスしましょう。
サーバーリプレイスしなかった場合のリスク
適切な時期を過ぎてもサーバーを交換しなかった場合、どのようなリスクが起こり得るのでしょうか。ここではサーバーリプレイスしなかったときのリスクについて解説していきます。データが消えてしまう
サーバーリプレイスすべき時期を過ぎても行わなかった場合、データが消えてしまうリスクがあります。劣化が進んだサーバーは、不具合が起こり最終的には故障してしまいます。故障してしまうとデータを失ってしまうリスクがあるため注意してください。運良くデータを復元できるときもありますが、定期的にバックアップされていなかった場合、新しく作られたデータは取り戻せません。最悪の場合、業務停止という事態に発展するケースもあり、時間もお金もかかってしまうでしょう。
セキュリティにおいてリスクが高まる
サーバーをいつまでも使い続けていると、いつか保守期間が終わってしまいます。保守期間が終わってしてしまうと、さまざまな問題を解決する更新プログラムが発行されないため、セキュリティーリスクが高まるのです。ぜい弱性をそのままにしておくとハッキングなどのリスクにさらされたとき、セキュリティーの穴を通過され、個人情報や企業情報を抜き取られる事態に発展してしまうでしょう。また、ウィルスやサイトの改ざんといった被害にあう可能性も高まります。
機能低下
電子機器なので長期間使用していると機能低下していきます。ストレージ容量が不足してしまったり、CPUが限界を迎えてしまったり、さまざまなケースが考えられます。トラブルが起こると処理する能力が低下してしまい、処理スピードが落ちてしまうでしょう。サーバーリプレイスの適性時期
適切な時期にサーバー交換しないと、さまざまなリスクにさらされてしまいます。ですから、定期的にサーバーを交換する必要があるのですが、どういった時期にサーバーを交換するのがよいのでしょうか。ここでは、サーバーリプレースの適切な時期を紹介します。サーバーの交換を検討する際の参考にしてください。
5年経過している
交換の時期は一般的に5年という目安があります。劣化や減価償却資産の観点から5年というのが目安となっているでしょう。ただし、使っている環境にもよるため、毎日休むことなく稼働しているのであれば5年以内で交換する必要があります。あくまでも5年という期間は目安程度に捉え、使用環境やサーバー自体の状態を考慮して時期を決めてください。
保守期間が終わってしまう
OSやハードウェアの保守期間を1つの目安として、保守期間が終わってしまう前にサーバーを交換しましょう。一般的にサーバーを交換するには、1年以上の時間を要します。また、費用もかかるため時間と費用ともに余裕を持った計画を立てる必要があるでしょう。さまざまなトラブルに見舞われないためにも、保守期間を意識してサーバーリプレイスの計画を立ててください。
たびたび故障する
長期間サーバーを使っていると、不具合が起こることもあるでしょう。特にサーバーリプレイスすべき時期が近づくと、不具合が頻繁に起こるようになります。頻繁に不具合が起こるということは、劣化してきている証拠です。一般的にサーバーリプレイスの時期は5年ほどといわれていますが、使用環境によっては5年以内に不具合が頻繁に起こるケースもあるでしょう。
サーバーが故障してしまい、データが破損したりなくなってしまったりしてからでは遅いので、早めにサーバー交換しておくことをおすすめします。たびたび不具合が起こったときには早急にサーバーリプレースを検討しましょう。
サーバーリプレースの注意点
サーバーを古いものから新しいものへと交換する「サーバーリプレース」をする際にはいくつかの点に注意する必要があります。ここではサーバーリプレースする際に注意しておきたいことをまとめてみましょう。早めに検討&予算の確保
サーバーのリプレースは、早めに計画を進めることが重要です。一般的には、サーバーの交換タイミングは約5年とされており、使用期間が長くなればなるほど老朽化が進み、故障するリスクも高まります。税務上、サーバーの原価償却資産が耐用年数6年となっているので、多くの企業は前年度の5年目に移行を行うケースが多いです。ただし、必ずしも5年で実施しなければならないというわけではなく、その前に新しいサーバーへ交換を検討する必要が出てくることもあります。
たとえば、24時間365日稼働しているサーバーの場合、頻繁に高負荷な処理業務を行っており、業務への負担が非常に大きいです。サーバーを酷使しているため故障するリスクも高く、5年を待たずに交換した方が良い場合もあります。
一方、日常的に負担が少ないサーバーや重要度の低いサーバーの場合には、5年以上経過してから交換するケースもあります。
サーバーの移行にはコスト面や作業による影響も伴うため、企業によってはタイミングが遅れるケースもあります。
古いサーバーから新しいシステムへの移行は費用がかかり、他の作業への影響もあるため、社内で調整や計画を入念に行う必要があります。
移行範囲や刷新の規模によって、必要なコストや期間は異なるため、具体的な計画を立てることが重要です。
OSやハードウェアのサポート終了直前に慌てて移行を行うと、問題が生じやすくなるため、余裕を持って計画し、事前にスケジュールを整えることが望ましいでしょう。
一般的にサーバーの切り替えには時間がかかるため、1年以上の期間が必要であると思っておくとよいです。スケジュールをしっかりと計画的に立てて、具体的な導入日や移行日、旧サーバーの撤去日を事前に決めておくことをおすすめします。
さらにリプレースには費用もかかるため、必要な予算を事前に把握し、しっかりと確保しておくことが不可欠です。ハードウェアやOS、ソフトウェア、運用・サポートを含めたトータルコストを見積もった上で予算を整えましょう。
予算を決める際には、すべての要件を満たそうとするとコストが膨らむ場合があります。詳細な仕様や条件については、予算に合わせて優先順位を付けて検討するのが賢明です。予算が限られている場合には最低限の仕様にとどめておくことをおすすめします。
データを安全に移行する
サーバーを新しく置き換える際に最も重要なのは、「安全かつ確実に移行作業を完了させること」です。安全にそして、確実に移行作業が行われなければ、企業活動にも大きな影響を及ぼしてしまうでしょう。サーバー交換に先立って、必ずデータのバックアップを取得しておくことが推奨されます。移行には定められた手順があるため、それに従って正確に作業を進めることが求められます。
手順に誤りがあると移行に失敗してしまい、サーバー内のデータがすべて失われる可能性も否定できません。たとえば、ファイルサーバーの移行中にエラーが発生すると、対象のデータだけでなく、保存されているすべてのファイルに障害が及ぶ可能性もあります。
こうしたトラブルを回避するためには、作業前に最新状態のバックアップを取っておくことが不可欠です。
さらに、万が一移行時に障害が起きた場合に備え、復旧作業の流れや手順を事前に整備しておくと安心です。突発的なトラブルで業務が停止すると、企業にとって大きな打撃となるため、万全の準備が求められます。
サーバーの停止時間は最小限にして以降後すぐに業務再開する
サーバーリプレースする際には、既存サーバーは停止する必要があります。一般的には利用者が困らないように深夜などの時間を利用してサーバーを停止させ、サーバー移行を行います。サーバーを停止する時間を最小限に抑えることで業務をストップさせずにリプレースできるでしょう。
停止するサーバーで提供しているサービスが企業にとって重要な事業の場合、サーバー停止時間がたとえ短時間であっても収益に影響が出てしまいます。停止時間はできるだけ短時間にし、業務への影響を最小限に抑えなければなりません。
サーバーを移行後は、すぐに業務やサービスを再開させる必要があります。サーバーを新しく交換したことによって、稼働している業務システムやサービスに影響が出てしまわないようにするためには、事前に十分なテストを行いましょう。
また並行運用期間などを設けておくなど、対策が必須です。並行運用とは移行前の旧サーバーと新しいサーバーを並行に稼働して、新しいサーバーが旧サーバーと同じように動くかどうかを確認するために、しばらく運用することです。
並行運用をした際に、処理が正しく移行されていると確認できた場合は、新しいサーバーへ完全に切り替えます。並行運用期間を設けておくと、スムーズに業務を再開できるでしょう。
サーバーリプレースを成功させるポイント
 サーバーリプレースを成功させるためにはいくつかのポイントがあります。ここではサーバーリプレースを成功に導くポイントをご紹介します。ぜひ参考にしてください。
サーバーリプレースを成功させるためにはいくつかのポイントがあります。ここではサーバーリプレースを成功に導くポイントをご紹介します。ぜひ参考にしてください。サーバーが故障する前にリプレースする
一般的にサーバーの交換は5年程度と言われています。問題なく使用できている場合、導入から5年以上経過していても、サーバーリプレースが面倒なのでギリギリまで交換しなくても大丈夫と感じてしまうかもしれません。しかしサーバーの老朽化は目には見えなくても、故障のリスクが増大しています。昨日までは何の問題もなく動いていたのに、今日になって突然壊れてしまった…という大事態が起きる可能性はゼロではありません。
サーバーが故障してしまうと、従業員はもちろん顧客にも大きな影響を及ぼします。サーバーが故障してしまう前にリプレースの準備を始めておく必要があるでしょう。
余裕を持ったスケジュールを組む
サーバーリプレースをするにあたって、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。サーバーリプレースをする場合、コスト面や作業面などの影響が大きく、社内全体での調整が必要です。サーバーリプレースをする際には早めに検討を開始する必要があります。新しいサーバーの調達やリプレースの手順作成、データのバックアップや事前検証など、リプレースに備えた必要な作業や要因を算出します。
機器や要因調達にどれくらいの期間が必要か、作業にどれくらいかかるのかを踏まえて、リプレースする時期を決定していくプロセスを策定しなければなりません。
既存環境を残す場合もあれば、大きく刷新する場合もあるので、リプレースにかかる期間やコスト、作業要員は会社によって異なります。基本的には1年以上の余裕があると安心です。
ハードウェアやOSのサポートが切れる直前になって慌ててリプレースすることがないように、時間に余裕をもって計画を立てましょう。
最適なシステム移行の方法を検討する
サーバーリプレースではサーバー上で稼働しているシステムやデータを移行するのが最も重要な作業です。稼働しているシステムの性質により、データ移行の方法はいくつかあります。リプレースを問題なく進めるためには、最適なシステム移行の方法を検討する必要があります。
データ移行の対象となるシステムの要件やデータ量などは事前に洗い出し、適切な移行方法を決定しておきましょう。
場合によっては、システムが使用しているソフトウェアの関係でリプレースが困難なケースもあります。その場合は、ハードウェアを延命させたり、システム自体をすべて刷新したりする判断が必要です。
要件の明確化
サーバーリプレースを行う場合には、適切なサーバーを選定しなければなりません。適切なサーバーを選定するためには、要件を明確化しておくことが大切です。新しいサーバーをいつまで使用する予定なのか、システムの負荷は今後どのように変化するのか、セキュリティの確保についてなど要件を明確化しておきます。サーバーの構成や必要なスペックは変化するため、それに見合ったサーバーを選定しなければなりません。
移行中のデータに破損に備える
リプレース作業中には、データが破損してしまう可能性があります。ファイルサーバーを移行している場合に、障害が発生してしまうと移行しているデータが破損する恐れがあるので注意が必要です。またそのデータ以外にも、ファイルサーバー内のすべてのデータが消えてしまうこともあります。
移行中のデータ破損に備えるために、必ずデータのバックアップは取っておきたいです。またバックアップデータの迅速な復旧方法も検討する必要があります。日常的に最新のバックアップを取っている状態であれば、復旧作業は簡単です。
障害発生を想定して、バックアップデータの復旧手順を決めておけば、スムーズにデータ移行対応ができます。
サーバーのスペックに余裕を持たせる
サーバーのスペックが足りなくなった場合に備えて、あらかじめスペックに余裕を持たせておく必要があります。業務規模が大きくなればなるほど、それに比例して高性能なスペックが必要です。スペックに対する想定が甘いとサーバーはダウンしやすくなります。また処理速度が遅くなり、処理に時間がかかるなどの問題も発生します。リプレース後にもスムーズな運用をするために、サーバーのスペックには余裕を持たせるようにしたいです。
サーバーリプレース完了まで並行運用を行う
サーバーを交換する場合、その規模によりますが、数ヶ月~1年程度かかる可能性も十分にあります。日常の業務を行いながらリプレースに必要な事前準備を行い、業務に支障が出ないように勧めましょう。リプレースに向けての準備は非常に大変です。新たなサーバーの要件定義や、ヒアリング、ハードウェアの調達などさまざまなプロセスがあります。リプレース前後にトラブルや不具合が起きても大丈夫なように、既存サーバーと並行運用させながら取り組むようにします。
サーバーの停止時間を最小限にする
サーバーリプレースをする際には、作業中に既存のサーバーを停止しなければなりません。そのサーバーで提供しているサービスが企業にとって重要な事業である場合もあるでしょう。サーバーを停止することで企業活動に大きな支障が出て、収益に影響を及ぼすこともあります。サーバーの停止時間はできるだけ最小限に留めることがポイントです。サーバーの停止時間をできるだけ短くすることで、業務への影響を極力減らすことにつながります。
また、サーバーの停止時間はもちろんですが、サーバーを停止する時間帯も重要です。日常業務やサービスにとって影響が少ない時期にサーバーリプレースの作業をする必要があります。連休期間や深夜にサーバーリプレースを行う企業は多いです。
データ移行後、スムーズに業務を再開する
サーバーリプレースでデータを移行後に、スムーズに業務やサービスを再開する必要があります。稼働中の業務システムやサービスへの影響を出さないようにするため、十分にテストを実施してからリプレースを行います。また、並行運用期間を設けることで業務やサービスへの影響を極力減らすことが可能です。データ移行に成功しても、その後の業務に支障が出てしまうと意味がありません。
長期にわたって業務ができない、サービスが利用できないとなると大変ですので、データ移行後に問題なく業務を再開できることをゴールとして考えます。
第三者保守を利用する
サーバーリプレースは期間やコスト、手間などがかかるため、企業によってはすぐに実施できないケースもあります。新しいサーバーを調達するのに時間がかかってしまう、要員を確保できないなど、サーバーリプレースができない理由はさまざまです。そのようなケースではサーバーリプレースの代わりに第三者保守を利用するのも1つの手段です。サーバーやストレージ、ネットワーク機器などのハードウェアの保守をメーカー以外の第三者が行っているサービスを第三者保守と言います。
メーカー以外の第三者によって行われている保守サービスを利用することで、保守切れとなった機器を継続利用できます。
また、リプレースの準備が整うまでのつなぎとして利用することが可能です。メーカー保守と比べると、安い価格でサービスを提供しているケースが多いため、コスト削減にもつながります。
リプレースの準備が間に合わない場合の一時的な対策として利用するのはもちろんのこと、第三者保守を活用することによってリプレースのサイクルを7~8年程度に延長できます。
クラウド型サーバーへの乗り換えを検討する
インターネット上に設置されたサーバーを利用するクラウド型への変更も選択肢の1つです。リプレースを検討する際には、クラウド型サーバーへの乗り換えについても検討する余地があります。クラウド型サーバーへ乗り換える場合、通常のサーバーのように5年ごとに交換する手間がなくなります。
ただし業務関連のデータをインターネット経由で利用することになるため、セキュリティ対策はこれまで以上に万全にしなければなりません。クラウド型サーバーにはメリット・デメリットどちらもあるため、それぞれを考慮した上で決めるべきです。
サーバーリプレースや構築の支援サービスを利用する
サーバーリプレースを自社だけで行おうとすると非常に大変です。とくにサーバーの規模が大きいと移行作業には時間も手間もかかります。自社での対応が難しいと感じた場合には、アウトソースして、支援サービスを利用するのもおすすめです。サーバーのリプレース作業や構築を支援するサービスを提供している会社は多数あるので、一度相談してみるとよいでしょう。
サーバーリプレースの手順を紹介
サーバーリプレースは次のような手順で行いましょう。現状の課題確認
サーバーリプレースをする際、まずは現状の課題を明確にすることが重要です。現在使用しているサーバーの老朽化や性能不足、セキュリティ面の不安などの技術的な問題に加えて使い勝手の悪さや処理速度などの運用上の課題も洗い出しましょう。実際にサーバーを利用している各部署のスタッフからていねいにヒアリングを行うことも効果的です。リプレース後のシステムに求められる条件を明確にすることによって実用的で効果的な導入計画を立てることができます。
計画と要件定義
課題の洗い出しが終わったら、サーバーリプレースの計画と要件定義を行います。移行対象や業務への影響を明記した計画書や提案書を作成し、方向性を明確にしましょう。要件定義では必要なサーバー台数やスペック、バージョン、使用するOS・ソフトウェア、周辺機器などを具体化します。また、将来の業務拡大やデータ増加も見据えた構成にすることをおすすめします。
見積もりと資金の確保
複数のメーカーに見積もりを依頼し、内容を比較して最適な提案を選びましょう。導入費用だけではなく、運用や保守費用を含めたトータルコストを見積もることが重要です。性能に余裕をもたせることは大切ですが、ハイスペックすぎると予算を圧迫する恐れがあるため、業務に適したスペックを見極めて無駄のない計画を立てましょう。また、計画と同時に資金の確保も必要不可欠です。
システム設計
見積もりと資金の確保ができたらシステム設計を行いましょう。要件定義にもとづいて新しいサーバーの構築を進める必要があります。ホスト名やIPアドレスなどを変更すると接続している端末側の再設定が必要になるケースがあります。そのため、業務への影響や作業負担を軽減するためにも可能な限り旧サーバーの設定内容を引き継ぐことが望ましいといえます。スムーズな移行を意識した設計を行いましょう。