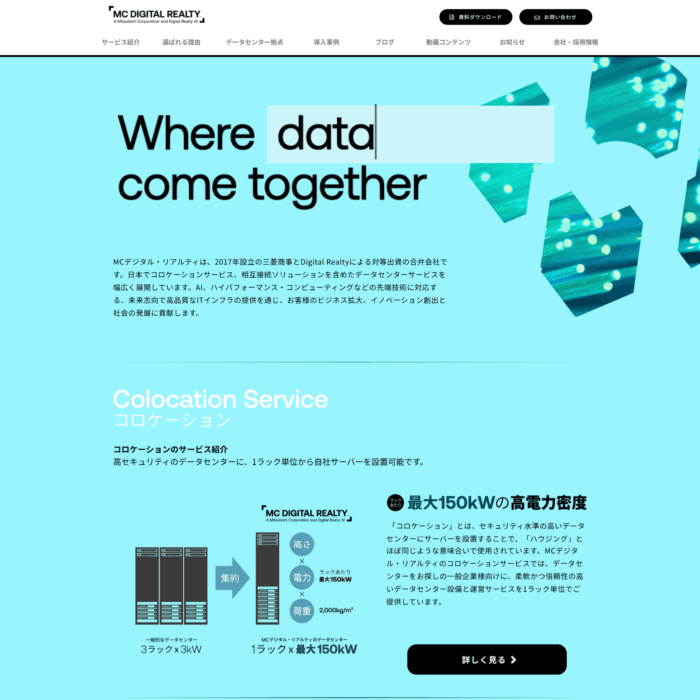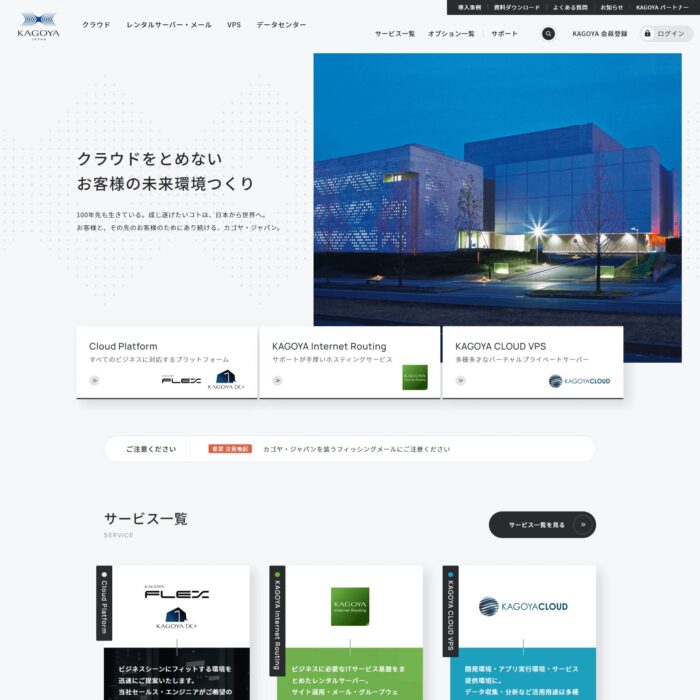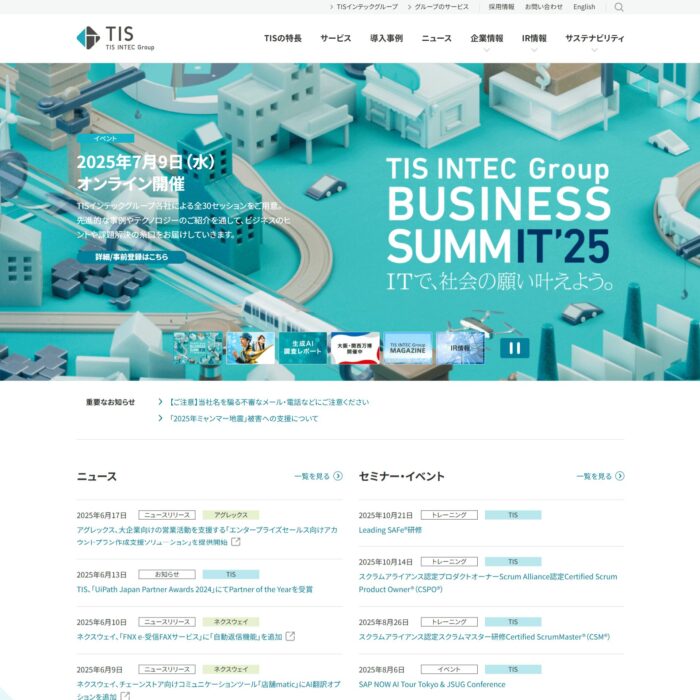ITサービス提供で欠かせないサーバーは、長く使用すると処理能力の低下や故障のリスクが高まっていきます。よって、適切なタイミングで新しい機器に入れ替えなければなりません。この記事では、サーバーリプレースがなぜ必要なのか、また実施を怠った場合に発生しうるリスクについても詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
サーバーリプレースの必要性
サーバーリプレースとは、老朽化したサーバーを新しい機器へ交換することを指します。リプレースには「取り替える」という意味があり、IT分野では旧型の機器やシステムを最新のものに入れ替える作業として使われることがほとんどです。安心して日々の業務を遂行するためには、パソコンやOSと同様に、サーバーについても万全な稼働体制を保つことが求められます。ここでは、サーバーリプレースの必要性について解説します。
業務遅延リスクを減らすため
サーバーに依存する業務やサービスがストップする前に交換し、業務遅延リスクを未然に防ぐのが、サーバーリプレースの主な目的です。サーバーが停止すれば、顧客対応の遅延や業績への影響にまで発展する可能性もあります。トラブルが起きる前に新しい機器へ切り替えることで、被害を最小限に抑えられます。スペック向上のため
業務であつかうデジタルデータ量は年々増加傾向にあり、過去の資料の長期保存や高解像度のコンテンツ処理、クラウド連携など、求められる処理能力やストレージ容量も拡大しています。導入から数年が経過したサーバーではこうしたニーズに対応できず、動作が遅くなる、容量が足りなくなるといった問題が起こりがちです。セキュアな状態の維持のため
ハードウェアやOSのサポート期間が終了してしまうと、脆弱性が修正されなくなり、セキュリティ面で大きなリスクを抱えることになります。サーバーは業務データや顧客情報など、重要な情報をあつかう機器だけに、保守対応ができない状態で使い続けるのは極めて危険です。サーバーリプレースの判断基準
 サーバーリプレースを検討する際には、単に使用年数だけでなく、業務の安定性やセキュリティ、コスト効率など多角的な視点から総合的に判断することが求められます。
サーバーリプレースを検討する際には、単に使用年数だけでなく、業務の安定性やセキュリティ、コスト効率など多角的な視点から総合的に判断することが求められます。以下のような場合には、リプレースを検討する判断基準になるでしょう。
ハードウェアの経年劣化とサポート終了
サーバーは長期間の運用により徐々にハードウェアが劣化し、性能や安定性が低下していきます。とくにハードディスクやメモリといった消耗部品は故障リスクが高く、障害が発生すると業務に直結する影響を及ぼします。さらに、メーカーが提供するハードウェア保守サービスは一定期間を過ぎると終了し、交換部品が入手できないケースもあります。こうした状況に直面した場合、トラブルが起きてから対応するのではなく、計画的にサーバーをリプレースする判断が求められます。
ハードウェアの寿命は一般的に5〜7年程度とされており、このサイクルを過ぎてからの運用は障害リスクを大きく高めるため、予防的な更新が重要です。
OSやソフトウェアのサポート状況
サーバーの安定運用には、利用しているOSやアプリケーションのサポート状況を見極めることが欠かせません。提供元のサポートが終了したソフトウェアはセキュリティ更新が行われず、脆弱性を突いた攻撃の標的となる可能性が高まります。とくに企業の基幹システムを支えるサーバーにおいては、サポート切れの状態で運用を続けることは大きなリスクを伴います。そのため、OSや主要ソフトウェアのライフサイクルを確認し、終了時期が近い場合にはリプレースを検討することが重要です。
加えて、ソフトウェアの更新が止まると最新のアプリケーションやセキュリティ機能との互換性が失われることもあり、企業の競争力低下にもつながります。
性能不足による業務効率の低下
近年の業務システムはデータ量や処理速度の要求が高まり続けています。導入当初は十分だった性能でも、利用ユーザー数の増加やシステム拡張によって応答速度が低下し、業務効率に悪影響を与えることがあります。アプリケーションの動作が重くなり、社員が作業を待つ時間が増えることで生産性が下がるケースも見られます。こうした性能不足を感じるようになった段階も、リプレースを検討すべき大きな判断基準となります。
とくに近年は、AIやビッグデータ解析など処理負荷の高い技術を活用する企業も増えており、それに耐えうる基盤を整えることが成長戦略上も不可欠です。
セキュリティ要件への適合性
サーバーは企業の情報資産を守る基盤であり、セキュリティ水準の確保が不可欠です。古いサーバーは最新の暗号化通信や認証方式に対応していない場合があり、外部からの不正アクセスに対して脆弱性を抱えるリスクがあります。さらに、セキュリティ監査や業界ごとの法令遵守要件に対応できないケースもあるため、システム全体のセキュリティ基盤を見直す際にはサーバーリプレースを合わせて検討する必要があります。
とくに金融や医療といった個人情報を扱う分野では、わずかな脆弱性も重大なインシデントに直結するため、定期的なリプレースは避けられない課題です。
運用コストの増大
老朽化したサーバーは電力消費が大きく、冷却効率も悪いため、ランニングコストが高くなる傾向があります。また、故障が増えれば保守費用や復旧対応のための人的コストも膨らみます。新しいサーバーへ移行することで、消費電力の削減や管理効率の向上が期待でき、トータルコストを抑制できる可能性が高まります。そのため、運用コストの増加が目立つ場合にも、リプレースを決断する重要な基準となります。
さらに近年では、クラウド環境を活用することで初期投資を抑えつつ最新の機能を利用できるケースも多くなっており、コストと性能のバランスを見極めることが企業の持続的成長に直結します。
サーバーリプレースの手順
サーバーリプレースを円滑に進めるためには、現状分析から運用開始後の監視まで一連の流れを計画的に行うことが、成功の鍵となります。以下に、サーバーリプレースの手順とその内容を解説します。現状分析と要件定義
まずサーバーリプレースを進める際には、既存環境の現状把握が不可欠です。稼働中のサーバーで利用しているアプリケーション、データ容量、アクセス頻度、処理性能などを詳細に分析します。そのうえで、今後必要となる業務要件やシステムの拡張性を踏まえて、新サーバーに求める要件を定義します。この段階で要件を曖昧にすると、その後の設計や選定に影響するため、十分なヒアリングと調査が必要です。
とくにクラウド移行を視野に入れる場合は、社内システムのどこまでをクラウドに適用するか、セキュリティ基準をどう満たすかといった判断も重要になります。
新サーバーの選定と調達
要件が明確になったら、それに適したサーバーを選定していきます。オンプレミスの物理サーバーにするのか、仮想化基盤を導入するのか、あるいはクラウドサービスを活用するのかを検討します。コストや運用体制、将来的な拡張性を考慮して最適な構成を決定し、調達を進めます。調達の際には納期やサポート体制も確認しておくと安心です。
また、クラウドを採用する場合には、ベンダーロックインやサービス停止時のリスクについても事前に評価し、冗長化を含めた設計を行うことが望まれます。
設計と構築
新しいサーバー環境を構築する前に、詳細な設計を行う必要があります。ネットワーク構成、セキュリティ設定、バックアップ体制などを具体化し、システム全体が安定して稼働できるように計画します。その後、サーバーのセットアップやOSインストール、必要なアプリケーションの導入を行い、要件に沿った環境を整えます。
構築段階ではテスト環境を利用し、問題がないことを確認することが望ましいです。とくに冗長構成や障害発生時のフェイルオーバー機能は、業務を止めないために必須の要素であるため、設計段階から盛り込むことが推奨されます。
データ移行と検証
構築が完了したら、既存サーバーから新サーバーへデータやアプリケーションを移行します。移行作業は業務に影響を与えないよう計画的に実施し、移行後は動作確認や性能テストを丁寧に行います。移行前には必ずバックアップを取得し、フルバックアップと差分バックアップを組み合わせて多層的に保護することが望まれます。保存先は外部ストレージやクラウドを併用し、障害時にも復旧できる体制を確保しておくことが重要です。
データコピー時には一時停止モードを活用して整合性を担保し、移行後にはレコード数やチェックサムを比較して正確に移行されたかを検証します。
さらにアプリケーションの動作確認、レスポンス速度の計測、業務フローに沿ったテストを行い、想定通りの結果が得られるかを確認します。
万が一問題があれば即時にロールバックできる準備を整えておくことで、業務への影響を最小限に抑えることができます。
本稼働と運用開始
検証が完了し問題が解決されたら、新サーバーを本格稼働させます。移行直後は予期せぬ不具合が発生することもあるため、一定期間は重点的に監視を行い、迅速に対応できる体制を整えます。その後は安定稼働を確認し、運用ルールや保守体制を明文化することで、長期的に安心して利用できる環境が実現します。
さらに、定期的なパフォーマンスレビューやセキュリティパッチの適用を怠らず、改善サイクルを回していくことがサーバーリプレースの成果を最大化するポイントとなります。
加えて、古いサーバーの後処理として不要データの削除や再利用可能機器の整理も行い、新環境へ移行した事実を明確に記録しておくと運用の透明性が向上します。
サーバーリプレースの期間
サーバーリプレースとひとことで言っても、実際には「どこまで入れ替えるか」によって必要な作業内容や期間は大きく異なります。ここでは、代表的なリプレースの種類と実施にかかる期間の目安を紹介します。ハードウェアの更改
最もシンプルなリプレース方法が、ハードウェアのみを入れ替える手法です。アプリケーションはそのまま利用し、サーバー本体やストレージなどの老朽化した機器だけを更新します。ただし、ハードウェアの更新に伴いOSやミドルウェアが新しいバージョンに変わることもあるため、場合によってはプログラムの軽微な修正が必要になることがあります。比較的短期間で実施でき、業務への影響を抑えやすいというメリットがあります。
リホスト(ITインフラの刷新)
リホストとは、既存の業務フローは変えずに、OSやミドルウェア、ハードウェアをまとめて刷新する手法です。現行と同じ言語を利用するため、動作検証後の移行が比較的スムーズに進みます。こちらも短期でのリプレースが可能で、老朽化によるリスク軽減と保守性の向上が期待できます。
リライト(コンバージョン)
リライトは、業務仕様は変えずに、OSやミドルウェア、ハードウェア製品を入れ替える手法です。リホストとは違い、現行とは違う言語でシステムを作り直します。設計書をもとに再構築を行うため、仕様そのものは維持しながら最新技術に対応できます。しかし、開発とテストの工程が必要となるため、比較的長い期間が必要になります。
リビルド(再構築)
リビルドは、既存システムの要件定義をもとにアプリケーション自体を作り直す方法です。仕様はそのままに、プログラムを全面的に新規開発するため、保守性や拡張性を高められる点がメリットです。ただし、開発工数が大きくなるため、プロジェクト期間は長期化します。パッケージ製品の利用
既存システムをパッケージ製品へ置き換える方法です。スクラッチ開発よりも機能の標準化が進み、運用コスト削減につながることがあります。ただし、現行業務をパッケージ仕様に合わせる必要があるため、移行計画と業務整理が重要となります。
全面刷新
システム全体を再設計し、まったく新しいシステムとして再構築する手法です。最も時間とコストがかかる手法ですが、将来のビジネス展開に合わせて柔軟性の高い構成を実現できます。このように、リプレースの手法によって必要な期間は異なります。ハードウェアの更改やリホストなど、短期で実施できる手法であれば1年未満で完了することがほとんどですが、リビルドや全面刷新の場合は1年以上かかるケースもあります。そのため、余裕をもって計画を立てることが重要です。
サーバーリプレースの適切な時期
以上のように、サーバーリプレースは、業務安定化とセキュリティ確保の両面で重要なIT施策のひとつです。しかしながら、サーバーの交換時期には明確なタイミングが設定されているわけではありません。よって、適切な時期を見極める必要があります。稼働年数と使用状況から判断する
一般的に、電子機器の法定耐用年数は5年とされています。これは会計処理上の基準であり、5年を過ぎたからといって即座に使えなくなるわけではありません。しかし、年数が経過するにつれて、ハードウェアの劣化やパフォーマンスの低下が徐々に進行し、障害発生のリスクが高まっていくのは事実です。5年を目安のひとつととらえ、早めに交換を判断しましょう。
事前に計画しておく
サーバーのリプレースには、一定の準備期間が必要です。とくに、大規模なネットワークや複数拠点にまたがるシステムを運用している企業では、業務への影響を最小限に抑えながら切り替えなければなりません。リプレースの必要性を感じた段階で、早めに計画を立て始めることが重要です。サーバーリプレースは単なる機器の更新ではなく、事業継続性を確保し、競争力を維持するための戦略的な投資といえます。
安定した業務運用を維持し、サイバーリスクやパフォーマンス劣化を未然に防ぐためには、適切なタイミングでのサーバー更新が欠かせません。
サーバーリプレースを行わないことによるリスク
古いサーバーを長期間にわたって使い続け、適切な時期にリプレースしないままでいると、業務や事業全体に甚大な影響を与えるリスクが高まります。企業の生産性低下
サーバーの劣化により、業務システムの動作が重くなったり、アクセス集中時に応答が遅れたりするトラブルが頻発すれば、業務の生産性は大きく損なわれます。パフォーマンスの劣化が慢性化すれば、顧客対応や意思決定にも影響がおよび、機会損失を招く恐れもあるでしょう。さらに深刻なのが、サーバーの突然の故障によって業務が完全に停止してしまうケースです。データが消失したり、バックアップからの復旧に時間を要したりすれば、取引先や顧客への信用にも悪影響が出かねません。
加えて、旧式のサーバーは新しいシステムやソフトウェアとの互換性に問題が生じることもあります。たとえば、最新の業務アプリケーションやセキュリティ対策ツールを導入したくても、旧式サーバーでは対応できないケースが増えています。
セキュリティの脆弱化
サーバー上で稼働しているOSのサポートが終了すれば、セキュリティ更新が受けられなくなり、新たに発見された脆弱性は放置されます。ひとたびサイバー攻撃を受ければ、機密情報の漏洩や不正アクセス、サービス停止などの被害が発生する可能性があります。その間、サービスの停止や品質低下が表面化すれば顧客満足度の低下を招き、企業のブランド価値に悪影響が及ぶかもしれません。
サーバーリプレースにはどれくらい費用がかかる?
サーバーリプレースにかかる費用は、導入するサーバーの規模や種類、性能によって大きく変動するため「いくら」と一概に断言することは難しいのが実情です。小規模なファイルサーバーであれば数十万円から導入可能ですが、企業の基幹システムを担うような大規模なものになると、数百万から数千万円規模になることも珍しくありません。
費用を左右する主な要因としては、サーバー本体の価格はもちろん、ネットワーク機器などの周辺機器、OSやソフトウェアのライセンス、そして設計・構築・データ移行などに関わる人件費が挙げられます。
そのため、まずは自社がどのようなサーバーを必要としているのか、要件を明確に定義することが、適切な費用感を知るための第一歩です。
サーバーリプレイスに必要な費用の内訳
サーバーリプレースの総額は、大きくわけて「ハードウェア」「ソフトウェア」「人件費」の3つの要素で構成されています。ここでは、それぞれの内訳について詳しく見ていきましょう。ハードウェア
ハードウェア費用とは、サーバー本体や、その周辺機器にかかる費用のことです。サーバー本体の価格は、企業の規模や用途に応じたスペックによって異なります。法人向けの小型エントリーモデルであれば10万円前後から、より高性能なラック型サーバーになると20万円から30万円程度が目安です。さらに、ルーターやスイッチといったネットワーク機器、停電時にサーバーを守る無停電電源装置(UPS)なども必要に応じて用意しなければなりません。これらの周辺機器も、性能や規模によって価格は変動するため、自社の環境に必要なものをリストアップしましょう。
ソフトウェア
ソフトウェア費用には、サーバーを動かすための基本となるOSや、特定の機能を提供するミドルウェア、業務用アプリケーションなどの購入費用やライセンス費用が含まれます。近年では、初期費用を抑えられるサブスクリプション形式のライセンスも増えています。ソフトウェアを選定する際には、機能だけでなく、ライセンス形態や長期的なコストも考慮して比較検討することが大切です。
人件費
人件費は、サーバーリプレースのプロジェクト全体を通して発生する費用であり、総コストの中でも大きな割合を占めるケースがあります。具体的には、現状の課題分析や新しいサーバーの要件定義、システムの設計、機器の設置と設定、データの移行作業、そして稼働テストなど、各工程で専門的なスキルを持つエンジニアの作業費が含まれます。
サーバーリプレイス時にコストを抑える方法
サーバーリプレースは高額になりがちですが、工夫次第でコストを大幅に抑えることも可能です。ここでは、賢くコストを削減するための3つの具体的な方法を解説します。クラウドへの移行
オンプレミスの物理サーバーから、クラウドサーバーへ移行することは、コスト削減の有効な手段の一つです。クラウドサービスを利用する場合、自社で高価なサーバー機器を購入する必要がないため、初期投資を大幅に削減できます。月々の利用料は発生しますが、ビジネスの成長や状況に合わせてCPUやメモリ、ストレージなどのリソースを柔軟に変更できるため、過剰なスペックに費用を払い続けるといった無駄を防げるでしょう。
リファービッシュサーバーの活用
リファービッシュサーバーとは、初期不良などで返品された製品をメーカーや専門業者が修理・整備し、新品同様の品質で再出荷される「整備済製品」のことです。新品と比較して価格が大幅に安いため、サーバーの調達コストを大きく抑えられます。単なる中古品とは異なり、専門家による厳しい検査を経て出荷されるため、品質面でも安心して利用できるでしょう。特に、現行システムの一部だけを先行してリプレースしたい場合や、大規模なリプレースまでの「つなぎ」としてサーバーが必要な場合に、リファービッシュサーバーの導入は効果的です。
第三者保守の活用
第三者保守とは、サーバーやネットワーク機器のメーカー保守期間が終了した後に、メーカー以外の専門業者が提供する保守サービスのことです。メーカーの公式保守が切れたからといって、必ずしもすぐにサーバーをリプレースする必要はありません。第三者保守を活用することで、既存のIT資産を継続して利用し、リプレースのタイミングを先延ばしにできます。
一般的にメーカー保守よりも安価なケースが多く、コストを削減しながらシステムの安定稼働を維持するための賢い選択肢と言えるでしょう。
サーバーリプレースを成功させるポイント
サーバーリプレースは、単に古い機器を新しくするだけの作業ではありません。コストを意識しつつ、将来のビジネス展開も見据えた計画的な進行が不可欠です。ここでは、リプレースプロジェクトを成功に導くために押さえておくべき7つの重要なポイントを解説します。早期の検討と綿密なスケジュール管理
サーバーの寿命は一般的に5年程度と言われており、この期間を超えると故障のリスクが高まります。突然の故障で業務が停止してしまう事態を避けるためにも、サーバーリプレースは早期に検討を開始するようにしてください。綿密なスケジュール管理を行うことで、予期せぬトラブルにも対応でき、スムーズな移行が実現します。
現状課題の洗い出し
サーバーリプレースは、現在抱えている問題を解決する絶好の機会です。「処理速度が遅い」「特定の時間帯にアクセスが集中して不安定になる」といった現状の課題を具体的に洗い出しましょう。関係部署の担当者にヒアリングを行い、現場のニーズを正確に把握することも欠かせません。これらの課題を明確にすることで、新しいサーバーに求められる要件が具体的になり、リプレースによる投資対効果を最大化できるでしょう。
将来性の考慮
サーバーリプレースを行う際には、現在の利用状況だけではなく、3年後、5年後のビジネスの成長や変化を見据えることが大切です。将来的にユーザー数やデータ量が増加することを見越して、拡張性のあるサーバー構成を検討してください。将来の事業計画と照らし合わせながら、柔軟に対応できるシステム基盤を構築することが、賢明な投資と言えるでしょう。
データ移行のリスク管理と徹底した準備
サーバーリプレースにおいて、最も慎重に進めるべき工程がデータ移行です。移行作業中に予期せぬトラブルが発生すると、最悪の場合、重要データが破損・消失し、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。こうしたリスクを回避するためには、徹底した準備が不可欠です。必ず事前に全データのバックアップを取得し、万が一の際の復旧手順を確認しておきましょう。
最適な移行タイミングの選択
新しいサーバーへの切り替え作業は、既存の業務に影響を与える可能性があります。そのため、業務への影響を最小限に抑えられるタイミングを選択することが重要です。多くの企業では、システムの利用者が少ない長期休暇中に移行作業を実施するケースが一般的です。関係部署と事前に調整し、業務への影響範囲と時間を明確にした上で、最適なタイミングを慎重に決定しましょう。
関係部署との連携
サーバーは、情報システム部門だけでなく、社内のさまざまな部署で利用されています。そのため、リプレースプロジェクトを円滑に進めるためには、関係部署との密な連携が欠かせません。移行スケジュールや、作業に伴う一時的なシステム停止の可能性など、想定される影響について事前に情報を共有し、理解と協力を得ることが大切です。
各部署の担当者と定期的に情報交換を行うことで、現場の要望を反映した使いやすいシステムを構築できるだけでなく、移行後のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
専門家の知見の活用
サーバーリプレースには、ハードウェアからネットワーク、セキュリティまで幅広い専門知識が求められます。自社に十分な知識を持つ人材がいない場合、無理に内製で進めようとすると、かえって時間やコストがかさんだり、トラブルの原因になったりする可能性があります。そのような場合は、経験豊富な外部の専門業者に相談・依頼することも有効な選択肢です。専門家の知見を活用することで、自社の状況に最適なサーバー構成の提案を受けられたり、複雑なデータ移行を安全かつスムーズに実施できたりします。
結果として、プロジェクト全体の成功確率を高め、リスクを低減することにつながるでしょう。