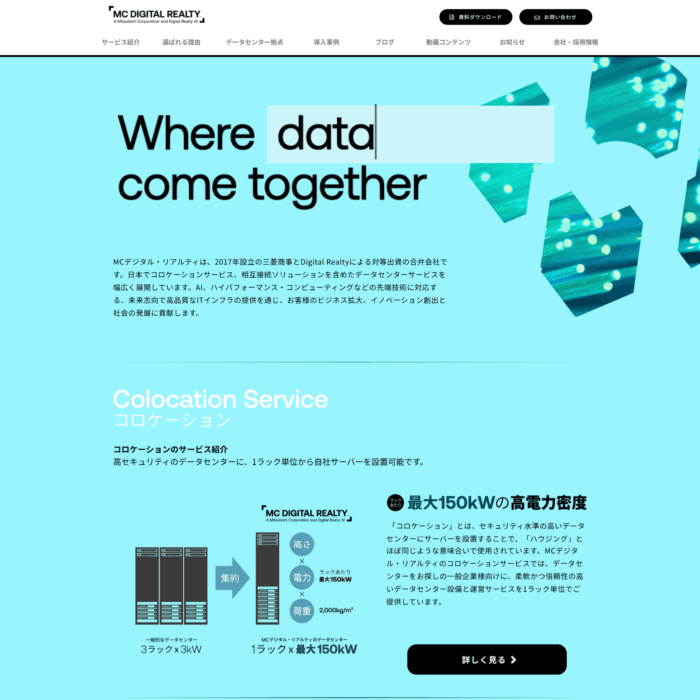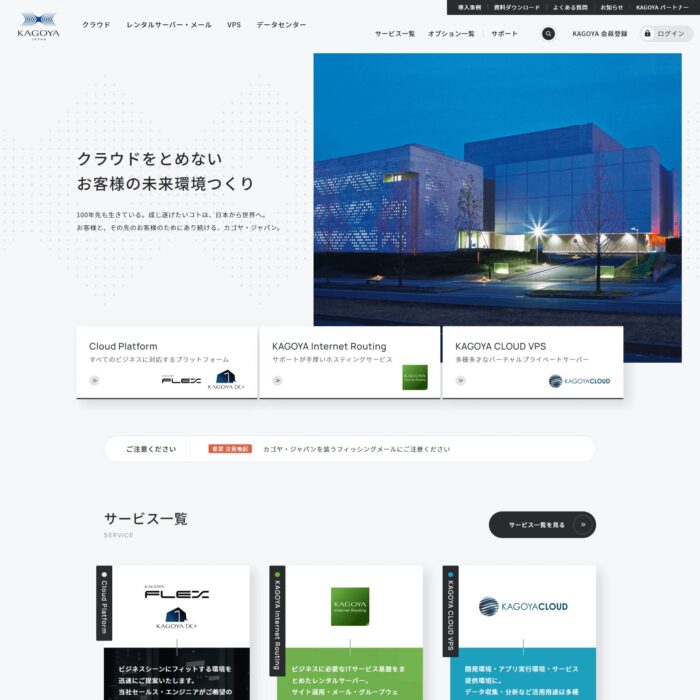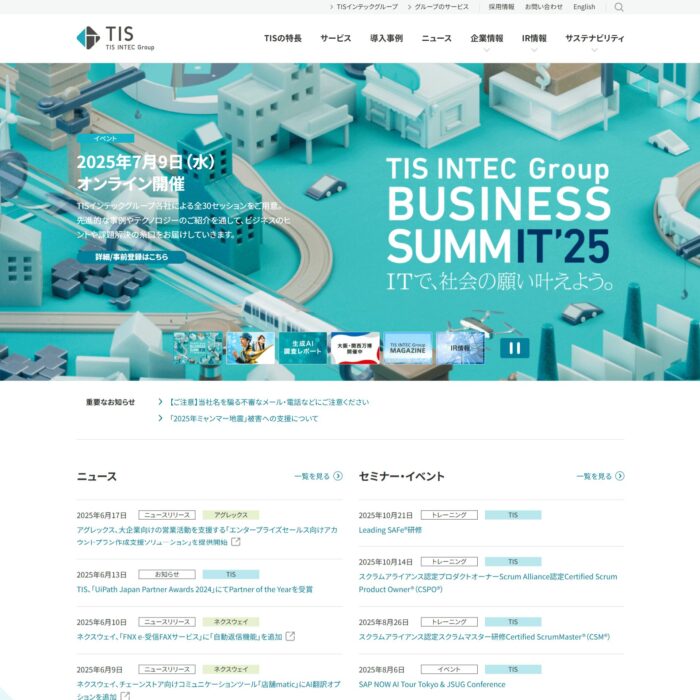IT機器やシステムの老朽化に伴い、多くの企業がリプレース時期を迎えています。そして、その際に発生する莫大なコストが課題となっています。企業のIT予算の7割近くが保守費用に充てられており、新規投資の予算確保が困難な状況です。本記事では、リプレースの基本概念や第三者保守を活用したコスト削減手法、実際の削減事例を解説します。
そもそもリプレースとは?
リプレースは「replace」という英単語が語源で、現在使用している機器やシステムを別の新しいものに置き換える作業のことです。情報システムの分野では、経年劣化したサーバーやネットワーク関連機器、データ保存装置などのハードウェア交換、あるいは業務システム全体の更新時に使われる専門用語となっています。
単純な修理対応とは異なり、処理能力の改善、新技術への適応、業務効率の向上といった複数の狙いを持って実行されるのが特徴です。
リプレースの狙い
リプレースの根本的な狙いは、業務システムの安定稼働を維持することにあります。機器は使用期間に比例して内部部品が摩耗し、トラブル発生の確率が高くなります。ソフトウェア面でも、新しい更新プログラムへの対応が困難になったり、セキュリティ面での危険性が増大したりする傾向があります。
こうした状況を放っておくと、業務の中断や機密情報の流出といった深刻な事態を招く恐れがあるため、計画的なリプレースの実行が求められます。
更新頻度の目安
通常、サーバー機器については5年程度での更新がおすすめです。これは税法上の減価償却期間が5年と定められていることも影響しています。大半の組織では、製造元による保守サポート終了(EOSL)のタイミングに合わせ、5年から7年のサイクルでシステム環境の刷新を進めています。ところが、更新時期に合わせて全面的な改革を試みようとすると計画は肥大化して内容も複雑になり、実施期間も延びてしまう傾向にあります。
製造元のサポート終了日という動かせない締切がある中で、システム担当部門は検証作業を含めた移行を完了させる必要に迫られ、厳しいスケジュールでの対応を強いられるのです。こうした状況下では、当初の見積もりを大幅に超える費用が発生することが珍しくありません。
リプレースによる第三者保守のメリット
第三者保守は、製造元とは別の専門企業が提供する機器メンテナンスサービスを指します。製造元のサポート期間が終了した後でも、故障修理や定期点検、トラブル対応といったサービスを受けられるのが特徴です。このサービスを利用することで、リプレースに伴う様々な問題を解消し、費用の大幅な圧縮が可能となります。第三者保守の最も重要な利点は、製造元が定めたサポート終了日以降も機器を使い続けられることです。
まだ問題なく動作している機器であっても、サポート期限に合わせて強制的に交換する必要がなくなります。組織が真に必要とする時期に、市場動向や経営方針を踏まえた理想的なスケジュールでリプレースを進められるようになることは魅力的です。
費用削減効果も顕著で、第三者保守の料金は通常、製造元サポートの70~80%程度に設定されています。年間で数億円に達する保守契約の場合、20~30%の削減でも相当な金額となります。
加えて、更新時には新品だけでなく、同じ性能を持つ割安な再生機器を組み合わせることも可能です。この方法により、すべて新品で構成する場合と比べて、費用を大きく抑えることが可能となります。
さらに、第三者保守では必要な機器のみを選んで更新することが可能です。全機器の一斉交換が不要となり、段階的で計画的な更新計画を立てられます。使える既存機器を破棄せず新しい環境でも有効活用できるため、投資効率が向上し、環境配慮の観点からも望ましい選択となります。
更新計画に遅れが生じた際も、第三者保守なら従来システムをサポート期限後も使用できるため、無理な短縮対応や品質低下を招く対策が不要です。これによって、リスク管理と品質維持を両立させることができます。
リプレースによるコスト削減事例
第三者保守を導入した組織での費用削減の実例を紹介します。ある組織では、ネットワーク機器約200台の更新においてすべて新品で構成した場合、設置作業500時間を含めて約6,000万円の見積もりとなりました。ところが、第三者保守を利用し、再生機器を組み合わせた同等性能の構成にしたところ、約1,200万円での実施が可能となりました。これは、80%という驚異的な削減率です。他の事例では、2億円の予算を計上していた更新計画を、第三者保守の導入により5,000万円で実現した組織があります。
この組織では、現行環境を綿密に調査し、新品交換が必要な機器、再生品で対応可能な機器、継続使用できる機器に分類しました。各機器に最適な対応方針を決定することで、費用対効果の高い更新を達成しています。
さらに別の組織では、サポート終了に伴う更新を検討していましたが、第三者保守による性能評価の結果、現行システムの継続利用に問題がないことが判明し、更新を見送って保守期間を延長しました。
この組織では、将来の更新時に製造元提案の半分程度のサーバー数で対応できることも分かり、約1億円の費用圧縮が見込まれています。